園長ブログ
 1
2
3
...
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
...
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


 いろいろな保育がありますが、一番大切な事は「お子さんがいつも対象物に対して受動的にかかわっているか?能動的にかかわっているか?」ということ。
いろいろな保育がありますが、一番大切な事は「お子さんがいつも対象物に対して受動的にかかわっているか?能動的にかかわっているか?」ということ。
いつも自分で決めて自ら関わると、学ぶことも深く、印象的になるように思います。 いかに能動的(主体的に)に関わらせるか? それには「選択制」が有効です。
お家でも何かさせたい時、「する、しない」を選ばせるのではなく「する方向でどちらをチョイスする?」にするとお子さんの機嫌が直って次へとスムーズに事が運ぶということが多くありませんか? 大人でもそうですが、ああしろこうしろと先が見えずに指示だけされる程、不安で不愉快なものはありませんね。 子どもだって見通しを持って主体的に動けるものなら動きたいのです。 ルールの範囲内でお願いしたいですけれどネ。 (保育園ではそのような時にはルールも一緒に覚えてもらいます。)
お約束を守る様に努力しながら、主体的に活動して(遊んで)いる様子です。 みんな没頭してよく遊んで(学んで)いました。
カテゴリー 園長ブログ
 これらの絵は今年の干支にちなんで製作活動をした子ども達の作品ですが、どの絵も伸び伸びとしていて辰の表情が豊かでいいですね。 製作過程で見せてくれただろう楽しそうな子ども達の表情や笑顔が目に浮かびますね。
これらの絵は今年の干支にちなんで製作活動をした子ども達の作品ですが、どの絵も伸び伸びとしていて辰の表情が豊かでいいですね。 製作過程で見せてくれただろう楽しそうな子ども達の表情や笑顔が目に浮かびますね。
さて、今年もこの「園のホームページ」では、保護者の皆様やご家族の皆様へ向けてはもちろんのこと、地域の皆様に向けても同様に、園の中の様子をお伝えすることによって、子どもたちが毎日どんな生活を送っていて、保育士・看護師・栄養士・園長が同じ理念の下、其々がどんな考えで日々の給食作りや保育を大切に思い、実践しているのか?等々、知って関心を持っていただけることにより、お家でも、地域でも、子どもたち一人ひとりを取り巻く環境が更に良くなっていってくれれば・・。という想いで作成しております。
それこそが保育園の職員に課された使命だと思うからです。 でも、みなさん、たとえこの使命が“保育所保育指針で告示されたもの”だからと言っても、どうしてこんなに沢山の職員が楽しそうに使命を果たしている(毎週、幾つもの記事を更新している)のだと思いますか? ・・・“それは、「子どもをとりまく環境が良くなって行けばいく程、子どもたちのキラキラした笑顔をたくさん見る事が出来、子ども達同士が共に育ち合い、自立に向かって行くことが出来る」ということが職員全体に深く浸透してきた。”ということと、元来保育園には「子どもの笑顔が好き!」「子どもを大切にしたい!」という想いの職員が集まってくる所だからなのでしょう。 保育を変えたら保育がもっと楽しくなって心に余裕が出てきたという職員も。 子どもの姿を見守れるようになると職員同士も見守れて、保育園内が穏やかなとても居心地のいい空間になってきていることを感じます。
「園のこだわり」をお読みいただけると顕著にお分かり頂けると思います。 但し、勘違いされると困ってしまうのでしっかりお伝えしなければ・・・と思うのですが、例えば1月5日の記事では、 この文章をお読みになって「先生達は見てるだけで何もしないの?子ども任せにしていて楽でいいわね・・(笑)」という誤認識をされると・・・頭が痛いです。 保育士は何もしていない訳でなく、それよりも子ども同士の素晴らしい育ち合う姿が素敵だったことをお伝えしたくて書いた記事ですね。 「すべきこと」「すべきでないこと」を見極め、心にちょっと余裕を持つと見えてきた(保育方法を変えたら見えてきた)事をお伝えして、お家でも実践するとこんな良い場面が見れますよ。一緒にしてみませんか?とお伝えしたかったのです。
子ども達には良い環境でいろいろな経験をさせてあげたい。人間同士の関わりも大切な経験、しかも人格形成のこの時期にはとても重要な事。 でも、昔のように子どもを連れて玄関を出れば子ども連れの誰かに出会う時代・・では無くなっています。タイミングが悪かったら例え公園でも出会わないことがあるこの少子化の時代。そんな中に在って、0歳児から6歳児までのお子さんが主体的に動いて毎日たくさんの関わりが持てる所と言ったら・・・それはもう保育園しかないのかもしれませんね。 そして、現代の保育・・・もっと言うと「少子化の時代に合った保育方法」をとっている保育園を見つけて入れてあげることが・・・お子さんを取り巻く保育環境を考えてあげること・・・に繋がって行くのかもしれません。 歓喜園は今年も保育環境についてまじめに取り組む集団でいたいと思います。 ご理解の程、宜しくお願い致します。
カテゴリー 園長ブログ
「食育」と一口に言っても、かなり広い範囲で多岐にわたって使われる言葉ですね。保育園では子ども達に親しみやすく分かり易い食育をと心掛けています。3才以上児さんには3つの食品群別に食品を分けてもらい、摂取しないと体がどんな風になってしまうかお話ししたり、畑で毎年いろいろなものを育ててみては食べてみたり、給食室の前に珍しい食材を置いてみたり・・。子どもたちが食材に興味が持てるような導入をしています。お家で出来る食育を「12月の給食だより」に分かり易く載せてありますので、是非ご参考になさってみてくださいね。
年末のこの時期は、特にご家族づれでスーパーなどに買い物に出かけたりしますね。お子さんと一緒に食品の色や形を楽しんだり、新鮮な食材の選び方や旬の食材を教えてあげたりして、食材に興味・関心が持てるようにする事も立派な食育です。年齢に合ったやり方で無理なく短時間ですると良いでしょう。 お子さんと一緒に調理をすることも、お子さんが興味を示してくれるようでしたら、ミニトマトを洗うとか、レタスをちぎる、皮をむくなど年齢に見合った事を考えてあげましょう。 それもまだ無理なようでしたら、テーブルを拭きやお皿並べ、自分の食べたお皿を片づけるなどがいいでしょう。
食べた物から身体は作られています。危険を避けたり、食材を選ぶ目を持つことも大切ですが、量や鮮度・旬などによっても含まれる栄養素の量が違いますから、そのようなことの知識を得る事も大切ですし、それを使い回せる知恵も必要ですね。 今の世の中、食料が無いことによる食育よりも、豊富にある食材の中から自分に合ったもの食べたいものを選んで上手に組み合わせて栄養を取りながら、いろんな楽しみ方が出来るようになっていくことこそが本当の意味での食育なのではないかな、と思います。
カテゴリー 園長ブログ
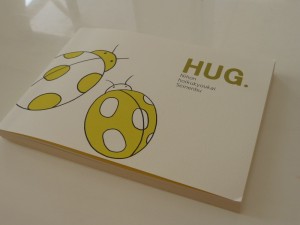 お仕事に子育てにと時間に追われ、毎日頑張っているお父さんお母さん 「子育てにちょっと疲れたな~」と感じた時や、「今日はちょっと怒りすぎちゃったかな?」と感じた時、お薦めの本があります。 それは・・・「HUG」という本。 (日本保育協会、青年部出版)・・・これは全国の保育園の現役副園長先生方が作った本です。
お仕事に子育てにと時間に追われ、毎日頑張っているお父さんお母さん 「子育てにちょっと疲れたな~」と感じた時や、「今日はちょっと怒りすぎちゃったかな?」と感じた時、お薦めの本があります。 それは・・・「HUG」という本。 (日本保育協会、青年部出版)・・・これは全国の保育園の現役副園長先生方が作った本です。
先日の「お遊戯会」の時にもご紹介しましたが、0・1・2歳児クラスの保護者の方の中で居合わせなかった方もいらっしゃいましたので、改めてご紹介します。 この本は子育てのポイントが書かれている子育て実用本で、1㎝位の厚みがあるのですが、中身は余白が多く、写真や挿絵と文章がまばらに入っていて、読んでいても圧迫感がありません。 それよりも、可愛い写真に魅せられてペラペラとページをめくって行くと、今度はてんとう虫のイラストに何だか・・・自然に癒されます。 毎日の仕事や子育てに追われ疲れたな~と思ったら、この本を手にとって見て下さい。 きっと、この本を置く頃にはちょっと肩から力が抜けて♪良い感じになっていると思います。
貸し出し本として25冊用意しました。 お子さんの絵本貸出カートで借りられます。連絡ノートや口頭でも良いので借りたい旨、お申し出ください。絵本袋の中に入れておきます。貸出期間は1週間です。 また、1階の子育て支援室にある「安心子ども文庫」で、お子さんが入園していない方でも借りる事が出来ます。 購入も出来ます。 手元に置いておきたい。プレゼントしたいからと、購入の希望も出てきています。 反響いいですよ。
カテゴリー 園長ブログ

 園庭にある小さな畑で大根が30本近く採れました。 以前年長さんが種まきをして育ててきた大根が、(と言っても、本当に大事に育ててくれたのは通園バスの運転手をしている倉島先生で、土を入れ替えたり籾殻を持ってきたり、収穫の時期だと教えてくれたりと私達保育士も栄養士も全て倉島先生におんぶに抱っこの状態でしたが…。)めでたく収穫の時期を迎えたので朝の戸外遊びの時間に大根を抜くことにしました。朝早く園庭に出た子からすっぽんと抜いていきます。初めての経験にカメラを向けると自然と笑みがこぼれました。
園庭にある小さな畑で大根が30本近く採れました。 以前年長さんが種まきをして育ててきた大根が、(と言っても、本当に大事に育ててくれたのは通園バスの運転手をしている倉島先生で、土を入れ替えたり籾殻を持ってきたり、収穫の時期だと教えてくれたりと私達保育士も栄養士も全て倉島先生におんぶに抱っこの状態でしたが…。)めでたく収穫の時期を迎えたので朝の戸外遊びの時間に大根を抜くことにしました。朝早く園庭に出た子からすっぽんと抜いていきます。初めての経験にカメラを向けると自然と笑みがこぼれました。
2歳児クラスの子ども達は、外遊びに出てきて抜かれた大根の山を見つけました。のぞき込んだり持ってみたりお友達と触った感触や重さの話でもちきりです。でもさすがに3歳前後の子どもたち、科学的な話題で集中力はそんなに長くは続きません。あっという間に外遊びへと移っていきました。まあなんと可愛いらしいことでしょう。子どもってほんとに素直ですね。
5歳児クラスの子どもたちは朝抜いた大根についてどうするか話し合いをし「サラダ」「煮物」「おみそ汁」「たくあん」・・・。などいろいろな案がでましたが、給食室の栄養士から近々作る昼食のメニューを聞き、その中から「大根とかじきの煮物」と「おみそ汁」に使ってもらおうと皆で決めました。また、おみそ汁に入れるときには夕涼み会の人参同様、包丁を使って切ってみたいと言う希望が多かったのでクッキング保育をすることにしました。
“この園での3年”という保育の中で、集中力の持続や話し合いの形式の認識、コミュニケーション力を獲得していきます。 これはきっと、朝の会帰りの会や“意図としてなるべく大人が介入して仕切ったりしない子どもたちの社会”で子どもたちが自ら獲得してきたコミュニケーション力であったり、“一円まる”(一円対話を子どもたちがそう名付けました)を楽しみながら獲得してきた成果なのでしょう。
カテゴリー 園長ブログ
10月中、保護者の皆様には何日も公開保育をお受けした為、駐車場や早お迎えなどでご協力を頂きました。 無事に公開保育を終える事が出来ました事は一重に保護者の皆様のご理解とご協力あってのことと深く感謝いたします。 ありがとうごさいました。
公開保育という、3日間、2回の研修でしたが、中でも21・22日は全職員、藤森平司先生(「21世紀型保育のススメ」著者。「子ども・子育て新システム」こども指針ワーキングチームなど、数多くの場でご活躍中)直々に保育環境についてアドバイスを受けたり、レクチャーを受ける事が出来、胸に落ちる事が多く、感心しきりで深く感銘を受けました。子ども達の興味関心と共に保育環境を見直す事はしていましたが、子ども達の全体的な成長と共に見直しすべき時か、年間でいつ検証すべき時なのか・・を忘れていました。すぐに取り掛かりました。考えているようでも更なる追求は、まだまだ在りそうです。保育は本当に奥が深いです。すればするほど、奥が深くなって行く感じがします。本当に遣り甲斐があります。
28日の上田市保育園連盟主催の公開保育に於きましては、県の保育専門相談員の先生方や市の保育課の保育指導主事の先生方、管理栄養士の先生方、そして上田市内の公私立保育園に所属する保育士さん・給食員さんなど大勢の方々がお見えになり研修が会が行われました。 午前中、子ども達の様子を見ていただき・・・、
・朝のマラソンは子どもが好きなコースを選んで、自分のペースで誰も休まず3分間走っていて凄かった。 ・個人個人の成長を見取り、尊重し、大切にした保育だった。 ・子ども達が自分で考え、気づいて行動している。 ・衣服の着脱も、大人に言われて脱ぎ着するのではなく、自分で“暑い”と感じたり“寒い”と感じて着脱するなど、気づく力が付いている。 ・お友達に教える時にも無理やりでなく、優しく教えてあげる事が出来ている。 ・3才以上児さんは60人が1クラス、自分のクラスとして保育士達の連携がとても良い。 ・子ども達の発達を把握した上で環境を用意し、いろんな目で見取り、見守って更なる育ちに繋がるようにしていっている。 ・子どもが求めてきた時にはそれにしっかりと向き合い応じることで、安心して遊びに熱中している姿がある。 ・ただ見ているだけでなく、子どもの育ちを見取っているからこそ、子ども達が何かを求めてきた時に、しっかりとそれに応える事が出来ている。 ・“子どもの心に寄り添い、子どもの力を信じる保育”という本園の理念に基づいてまさに実践できている。
・・・という感想をいただきました。
私立ならではの“特色のある保育”が見られた。・・とも感想をいただき、これからも全職員で子どもたちを見守って行きたいと思います。 そして、こうして保育園から発信することで保育士・栄養士・看護師、全職員が誇れる職場であったり、保護者の皆様、地域の皆様が誇らしく思っていただける保育園でありたいと願っています。 その為にも、これからも「見守る保育」で子ども第一に、「丁寧な保育」を続けて行こうと思います。
保護者の皆様、8年に一度の事とはいえ、半日お仕事をお休みして研修の場を用意していただき、ありがとうございました。 研修の成果や課題を検証して、以降の「保育」でお返しして行きたいと思います。
最後に、ご指導いただきました諸先生方はじめ他園の先生方、当園のホームページや理念を良く見てきて下さり、理解しようとして下さったこと、又、その上で意見や感想を言って下さったことに感謝申し上げます。 ありがとうございました。
カテゴリー 園長ブログ
新園舎になりそろそろ4年になります。大きな2階建ての園児達のお家は、1階が3歳未満児用、2階が3才以上児用になっています。そして3・4・5歳児の生活する場所が2階の一番奥のせいか、道路から、或いは玄関あたりではとても静かな保育園になっています。
1階の0・1歳児のクラス近くでは、芝生の園庭も広がり、本当に穏やかでゆったりとした時間が流れていますが、2歳児のクラスになるとだいぶ賑やかです。 2階の3・4・5歳児クラスに至っては更に賑やかな声や音がしています。
1階はミルクを飲んだり午前寝を必要とするお子さんをはじめとする30名程のところ、2階は60名程、しかもだいぶ自分の意のままに体の自由が利くお子さん達で人数も2倍。子ども達のはしゃぐ声。他にもいろいろな音が聞こえてきます。
しかし、良く聞いていると 唯、騒々しいわけではないのです。 子どもたちが観察した物や図鑑を見ながら楽しそうに会話している声であったり、ブロックや積木をどう繋げようか意見を出し合っている声であったり・・。いろいろな場所でいろんな場面が展開されています。 そのどれもが「人と交わること」で生じる大切な学習の場面です。
園舎の外からはなかなか見えないいろいろな事や、子ども達の育ちを解説してお伝えして行きたいと立ち上げた園のホームページです。 この「園長ブログ」も同様です。「園のこだわり」や「最新のニュース」と重なるところがあるかもしれませんが、「保育に関する気づき」や「子どもを取り巻く環境」などについても、多くの保護者の方々や地域の方々、そして、当園の保育に興味を持たれた方々に読んで頂けると嬉しく思います。
カテゴリー 園長ブログ
 1
2
3
...
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
...
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


 いろいろな保育がありますが、一番大切な事は「お子さんがいつも対象物に対して受動的にかかわっているか?能動的にかかわっているか?」ということ。
いろいろな保育がありますが、一番大切な事は「お子さんがいつも対象物に対して受動的にかかわっているか?能動的にかかわっているか?」ということ。
 これらの絵は今年の干支にちなんで製作活動をした子ども達の作品ですが、どの絵も伸び伸びとしていて辰の表情が豊かでいいですね。 製作過程で見せてくれただろう楽しそうな子ども達の表情や笑顔が目に浮かびますね。
これらの絵は今年の干支にちなんで製作活動をした子ども達の作品ですが、どの絵も伸び伸びとしていて辰の表情が豊かでいいですね。 製作過程で見せてくれただろう楽しそうな子ども達の表情や笑顔が目に浮かびますね。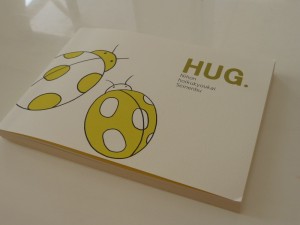 お仕事に子育てにと時間に追われ、毎日頑張っているお父さんお母さん 「子育てにちょっと疲れたな~」と感じた時や、「今日はちょっと怒りすぎちゃったかな?」と感じた時、お薦めの本があります。 それは・・・「HUG」という本。 (日本保育協会、青年部出版)・・・これは全国の保育園の現役副園長先生方が作った本です。
お仕事に子育てにと時間に追われ、毎日頑張っているお父さんお母さん 「子育てにちょっと疲れたな~」と感じた時や、「今日はちょっと怒りすぎちゃったかな?」と感じた時、お薦めの本があります。 それは・・・「HUG」という本。 (日本保育協会、青年部出版)・・・これは全国の保育園の現役副園長先生方が作った本です。
 園庭にある小さな畑で大根が30本近く採れました。 以前年長さんが種まきをして育ててきた大根が、(と言っても、本当に大事に育ててくれたのは通園バスの運転手をしている倉島先生で、土を入れ替えたり籾殻を持ってきたり、収穫の時期だと教えてくれたりと私達保育士も栄養士も全て倉島先生におんぶに抱っこの状態でしたが…。)めでたく収穫の時期を迎えたので朝の戸外遊びの時間に大根を抜くことにしました。朝早く園庭に出た子からすっぽんと抜いていきます。初めての経験にカメラを向けると自然と笑みがこぼれました。
園庭にある小さな畑で大根が30本近く採れました。 以前年長さんが種まきをして育ててきた大根が、(と言っても、本当に大事に育ててくれたのは通園バスの運転手をしている倉島先生で、土を入れ替えたり籾殻を持ってきたり、収穫の時期だと教えてくれたりと私達保育士も栄養士も全て倉島先生におんぶに抱っこの状態でしたが…。)めでたく収穫の時期を迎えたので朝の戸外遊びの時間に大根を抜くことにしました。朝早く園庭に出た子からすっぽんと抜いていきます。初めての経験にカメラを向けると自然と笑みがこぼれました。